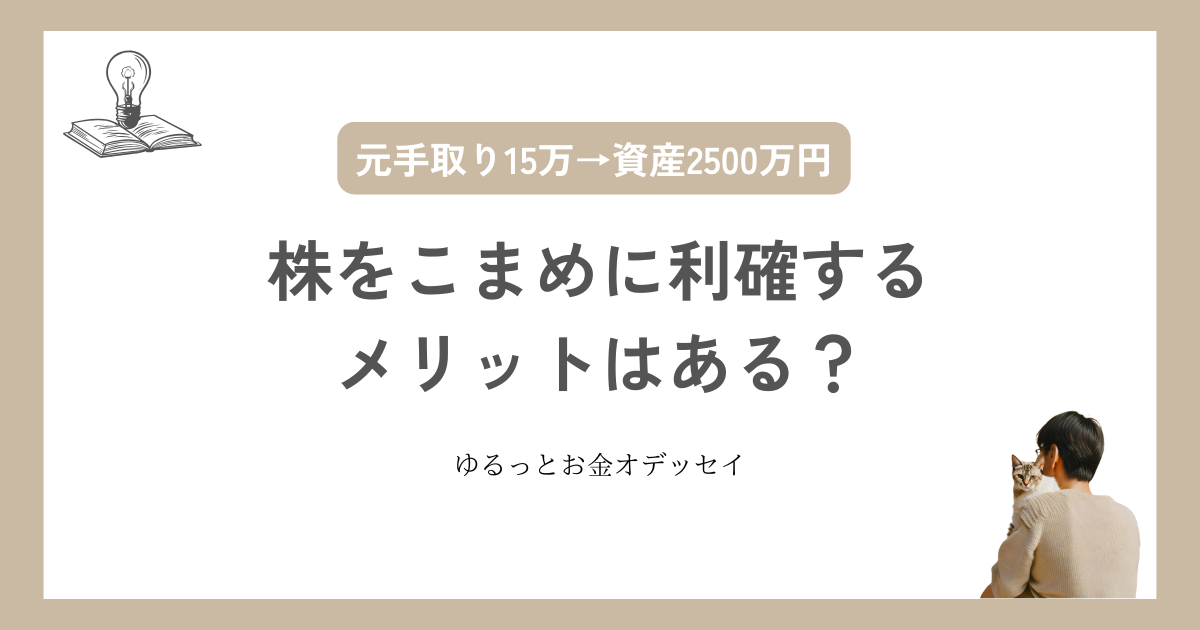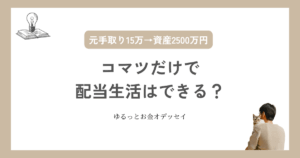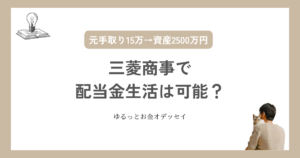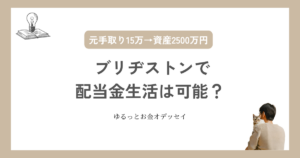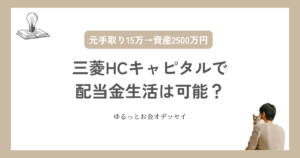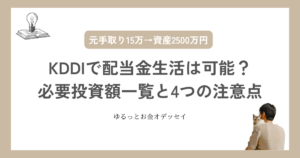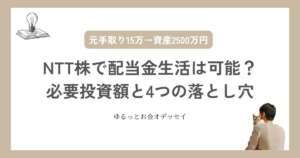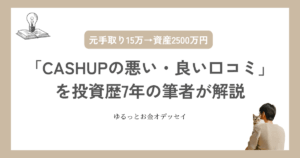株式投資で利益が出たとき、「このまま保有を続けるべきか、それとも売却すべきか」という判断に迷う方は多いでしょう。
特に、株価が上昇基調にあるときは、「今のうちに利益確定しておこう」という誘惑に駆られます。
確かに、株をこまめに利確するのは一見賢明な戦略に思えるものです。
しかし、実際には頻繁な売買は投資成績を大きく損なう可能性があります。なぜなら、目に見えないコストや機会損失が多く潜んでいるからです。
「高く売って安く買い直せば儲かる」という単純な発想は、しばしば裏目に出てしまいます。
では、株をこまめに利確することには、実際にどのようなデメリットがあり、どのような場合に売却を検討すべきなのでしょうか。
本記事では、投資歴5〜6年の筆者の知見を交えながら、株式投資における適切な利益確定の考え方を解説していきます。
株をこまめに利確するメリットは基本的になし
株式投資でこまめに利確することは、お菓子の箱からチョコレートを1個ずつ食べるようなものです。
一時的な満足は得られますが、結果的に箱が空になるのが早くなってしまいます。
同じように、頻繁な売買は一時的な利益は得られても、長期的な資産形成の観点からは得策ではないのです。
例えば、1万円で購入した株式が1万2千円になった時点で売却すると、手数料や税金で約500円が引かれてしまいます。
| ステップ | 金額 | 手数料・税金(例) | 残額(投資可能額) |
|---|---|---|---|
| 1. 初回購入 | 10,000円 | なし | 10,000円 |
| 2. 売却(株価上昇) | 12,000円 | -500円 | 11,500円 |
| 3. 再購入 | 11,500円 | -500円 | 11,000円 |
残った1万1500円で再度同じ株を購入しようとすると、さらに手数料がかかり、実質的な投資金額は1万1000円程度まで目減りしてしまうでしょう。
これは、100円の商品を105円で売って、また100円で買い直すようなもの。
むしろ、優良企業の株式は植物の種のように育てていく方が賢明です。
水をやり、日光を当て、時間をかけて大きく育てるように、企業の成長とともに株価も上昇していくのを待つことで、より大きな果実を得られる可能性が高くなります。
 ひろ
ひろ全ての企業が同じように成長するわけではないため、「どの銘柄を選ぶのか」がポイントです。
利確して買い直しするメリットはある?
株式を利確して買い直す戦略がメリットを持つのは、限られた状況に限られます。
例えば、りんごの木が病気になってしまったように、投資先企業に深刻な問題が発生した場合です。



また、より実りの多そうな別の果樹(より良い投資機会)を見つけた時にも、植え替え(銘柄の入れ替え)を検討する価値があるでしょう。
ただし、「今のりんごを収穫して、また新しい苗を植える」ような短期売買は、非常にリスクの高い戦略です。
なぜなら、株価の動きを正確に予測することは、ベテランの農家でも天候を完璧に予測できないのと同じように、極めて困難だからです。
売却後に予想に反して株価が上昇し続けると、より高値で買い直さざるを得なくなることも少なくありません。
むしろ、定期的な手入れ(投資計画に基づく運用)を続け、時には剪定(ポートフォリオのリバランス)を行いながら、長期的な視点で育てていく方が、より確実な収穫(リターン)を期待できるのです。
投資の本質は、優良企業という肥沃な土地に種を蒔き、その成長を待つことにあります。
しかし、一方で「株を利確する目安」は存在するので、次章であらためて確認していきましょう。
株を利確する目安


「株をこまめに利確するメリット」はあまりないと考えています。
しかし、適切な利確を行う目安は存在するので、きちんと目を通しておくといいでしょう。
以下の3つの状況は、株式を売却する重要な判断基準となります。
- 目標利益に達したとき
- 企業の状況が変化したとき
- 保有株以外で魅力的な投資先が見つかったとき
目標利益に達したとき
株式投資では、事前に目標とする利益を設定しておくことが大切です。
例えば、購入価格から20%上昇したら半分を売却する、といったルールを決めておくのです。
これは、お菓子作りでタイマーを使うのと同じように、感情に流されない判断基準となります。
具体的な例を挙げると、10万円で購入した株式が12万円(20%上昇)になったら6万円分を売却し、残りの6万円分はさらなる値上がりを期待して保有を続けるといった方法です。
段階的に売却することで、上値を追いながらもリスクを抑えることができます。
また、業界や企業の特性によって目標値を変えることも重要です。
成長企業であれば30%以上の上昇を目指し、安定企業であれば10%程度の利益確定を考えるといった具合です。
企業の状況が変化したとき
企業の状況変化を見極めることは、植物の健康状態をチェックするようなものです。
例えば、
- 業績の悪化
- 経営陣の不祥事
- 主力製品の競争力低下
などは、植物の葉が黄色くなったり、虫が付いたりするのと同じように、警戒すべきサインとなります。
具体的には、四半期決算で2期連続の減益、新製品の発売延期、重要な人材の流出といった出来事は、売却を検討するきっかけとなるでしょう。
特に、投資した理由が失われた場合(例:成長戦略の変更、配当方針の見直しなど)は、すみやかな売却を考える必要があります。
ただし、一時的な業績悪化なのか、構造的な問題なのかを見極めることも重要です。



一時的なもので、その後に回復する兆しがあれば保有する姿勢を取ります。
台風での一時的な売上減少と、市場シェアの恒常的な低下では、対応を変える必要があるのです。
保有株以外で魅力的な投資先が見つかったとき
より良い投資機会を見つけることは、より美味しそうな果物を見つけたときの選択に似ています。
手持ちのりんごも悪くないけれど、目の前にみずみずしい桃があれば、買い替えを検討する価値があるでしょう。
例えば、現在保有している製造業の株式が年間5%程度の成長が見込めるのに対し、新興のIT企業で年間20%以上の成長が期待できる銘柄を見つけた場合です。
このとき、リスクとリターンのバランスを考慮しながら、ポートフォリオの組み替えを検討します。
ただし、「隣の芝生は青く見える」という言葉があるように、新しい投資先の魅力を過大評価しないよう注意が必要です。
手数料や税金などのコストを考慮しても、十分なメリットがあるかどうかを冷静に判断することが大切なのです。



筆者は5〜6年ほど投資をしていますが、買い替えることはあまりしませんでした。
株をこまめに利確するデメリット5選
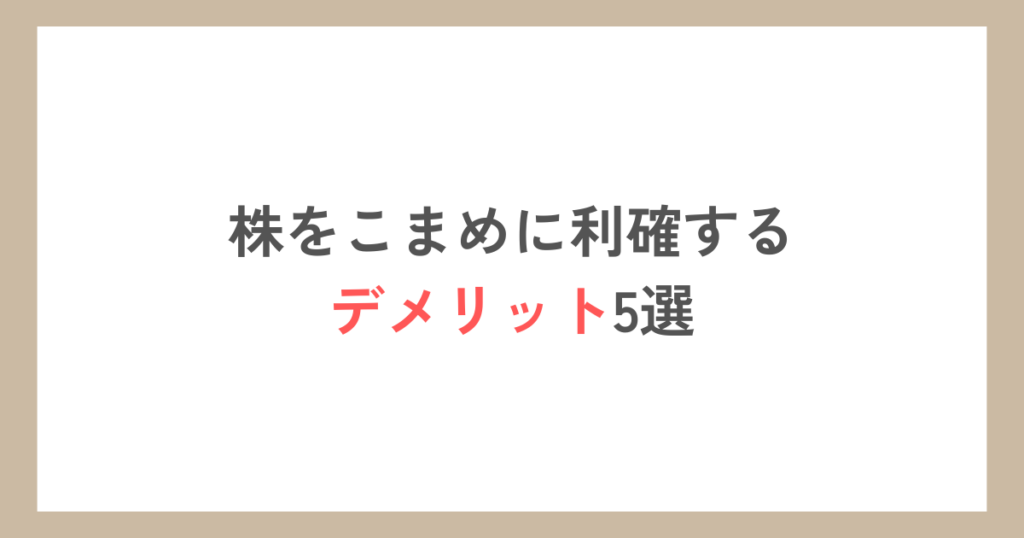
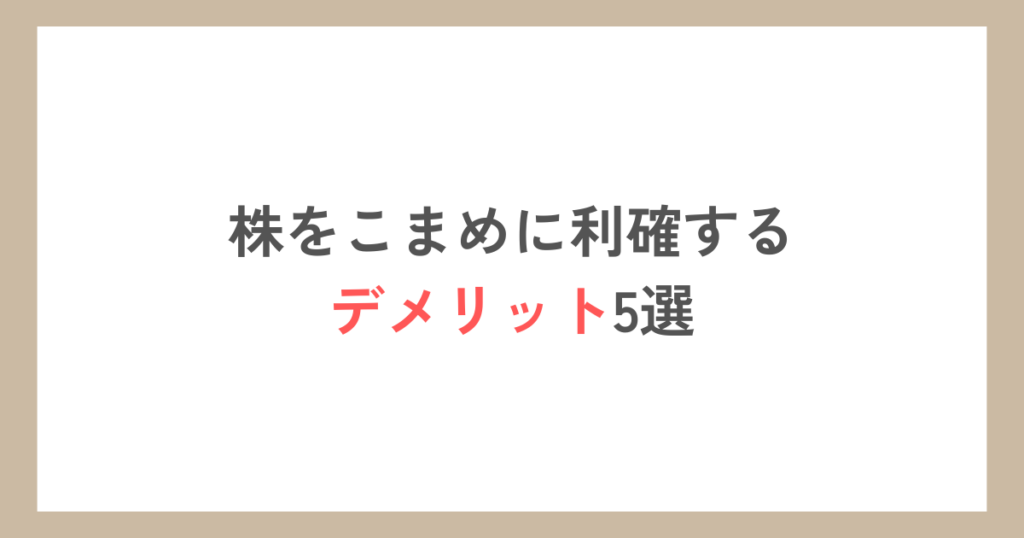
株式投資において、頻繁な売買は一見賢明な戦略に思えますが、実は多くのデメリットが隠れています。
特に初心者の方は、以下の5つのデメリットをしっかりと理解しておく必要があるでしょう。
- 税金が余計に発生する
- 複利効果が失われる
- 取り引きコストが増える
- 買い直しするタイミングを逃す
- 感情的な行動をとりやすくなる
これらは投資の成果を大きく左右する重要な要素です。
また、投資初心者は、以下の記事にも目を通しておくのをおすすめします。
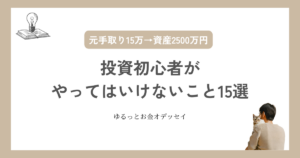
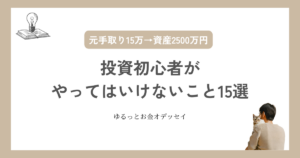
①税金が余計に発生する
株式投資で利益が出た場合、約20%の税金(所得税15%と住民税5%)が課されます。
例えば、10万円で購入した株式が12万円になって売却した場合、得られた利益2万円に対して4,000円の税金が発生します。
2万円×20%=4,000円ですね。
頻繁に売買を繰り返すと、その都度上記のような税金が発生してしまいます。
たとえば、年に10回の売買で毎回2万円の利益を出した場合、合計4万円もの税金を支払うことになるでしょう。
一方、1年間株を保有し続けて20万円の利益を出した場合の税金は同じ4万円です。
つまり、株をこまめに利確すると税負担が実質的に増えてしまうのです。



長期投資が目的にもかかわらず、株をこまめに利確していては、矛盾した投資スタイルになってしまいますね。
②複利効果が失われる
複利効果とは、「利益が新たな利益を生む」という投資における重要な概念です。
例えば、100万円の投資が10%の利益を生み、その110万円がさらに10%の利益を生むと121万円になります。これが複利効果の基本的な仕組み。
しかし、株をこまめに利確してしまうと、複利効果が大きく損なわれます。
具体的な例を挙げると、100万円の投資で10%の利益(10万円)が出た時点で売却(110万円)し、税金2万円を支払うと、次の投資に使える金額は108万円です。
これが10%の利益を生むと約119万円となり、先ほどの121万円と比べて約2万円も差が出てしまうのです。
| 項目 | 複利運用の例 | こまめに利確の例 |
|---|---|---|
| 初期投資 | 100万円 | 100万円 |
| 1回目:10%の利益発生 | 100万円 → 110万円 | 100万円 → 110万円 |
| 利確時の税金 | 売却しないため課税なし | 利益10万円の20% → 2万円を支払い |
| 次の投資資金 | 110万円(そのまま再投資される) | 110万円 – 2万円(税金) = 108万円 |
| 2回目:さらに10%の利益 | 110万円 × 1.1 = 121万円 | 108万円 × 1.1 ≈ 119万円 |
| 結果(差額) | 121万円 | 約119万円 |
- 利確をしない場合(複利効果):121万円
- こまめに利確をした場合:約119万円
上記の差は、投資期間が長くなればなるほど大きくなっていきます。
10年、20年という長期で見ると、複利効果の違いは数百万円規模の差となることも珍しくありません。
そのため、不必要な売買は避け、できるだけ長期投資を心がけることが賢明です。
③取り引きコストが増える
株式の売買には、必ず証券会社に支払う手数料が発生します。
例えば、株式を10万円分購入する場合、証券会社によって異なりますが、おおよそ100円から500円程度の手数料がかかると思います。
同様に、売却時にも手数料が必要になります。
具体的な計算例を見てみましょう。
1回の取引で往復500円の手数料がかかると仮定します。
月に5回の売買を行うと、手数料だけで月2,500円、年間では3万円もの費用が発生してしまいます。
手数料の負担は、投資金額が少ない場合、利益の大きな部分を占めることになるでしょう。



ただし、ネット証券のほとんどは取り引き手数料は0円であることが多いです。
株をこまめに利確するなら、取り引きコストを理解したうえで行うのが賢明です。
④買い直しするタイミングを逃す
株式を売却した後、「どのタイミングで買い直すか」という判断は非常に難しい問題です。
例えば、100円で購入した株式を120円で売却した後、110円まで下がったところで買い直そうと考えたとします。
しかし、実際には株価が予想に反して130円まで上昇してしまい、結果的により高い価格で買い直さざるを得なくなることも少なくありません。
特に、業績の良い優良企業の株式は、一度売却してしまうと、なかなか買い戻すタイミングが見つからないことがあります。
「もう少し下がってから」と待っているうちに、株価が上昇を続け、最初の売却価格を大きく上回ってしまうことも珍しくないのです。



経験上、「今が買い時」と思ったときが買うタイミングだったりします。
売却後の再投資タイミングを見極めることは、プロの投資家でさえ困難を伴う作業です。
むしろ、長期保有を基本とし、必要な場合にのみ売却を検討する方が賢明でしょう。
⑤感情的な行動をとりやすくなる
頻繁な売買は、投資家の心理面に大きな影響を与えます。
例えば、株価が上昇したときの「もっと上がるかもしれない」という期待や、下落したときの「これ以上下がる前に売りたい」という不安が、冷静な判断を妨げてしまうのです。
具体的には、株価が上昇トレンドにあるときに利益確定の誘惑に負けて売却し、その後さらなる上昇を見送ってしまうケースがあります。
反対に、株価が下落しているときに焦って売却し、その直後に反発上昇するといったことも少なくありません。
このような感情的な売買を繰り返すことで、本来得られたはずの利益を逃してしまう可能性が高くなります。
投資の成功には、感情をコントロールし、長期的な視点で冷静に判断する力が必要なのです。
まとめ
株式投資において、こまめな利益確定には多くの落とし穴が潜んでいます。
税金や手数料による実質的な利益の目減り、複利効果の損失、感情的な判断によるミスなど、短期的な売買は思わぬデメリットを生む可能性が高いのです。
ただし、これは「絶対に売却してはいけない」という意味ではありません。
目標利益の達成時や、企業の状況変化、より良い投資機会の発見など、売却を検討すべき適切なタイミングは確かに存在するでしょう。
重要なのは、感情的な判断ではなく、明確な基準に基づいて投資判断を行うことです。
優良企業への投資は、良質な果樹を育てるように、適切な管理と十分な時間をかけることで、より大きな果実をもたらしてくれるはずです。
賢明な投資家は、短期的な誘惑に負けることなく、長期的な視点で資産形成を進めていくことが大切なのです。