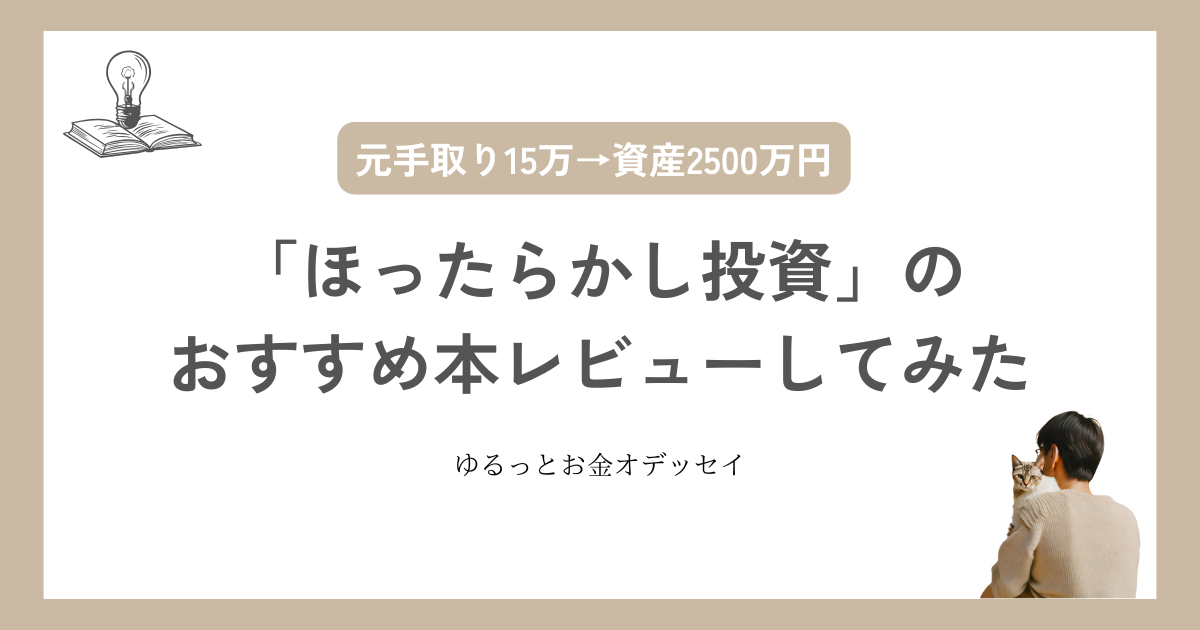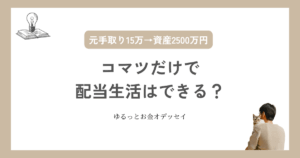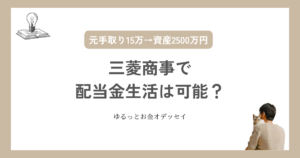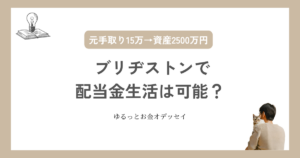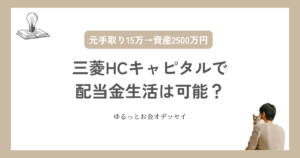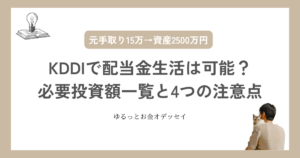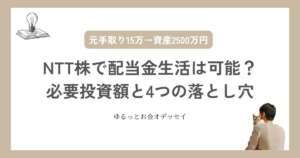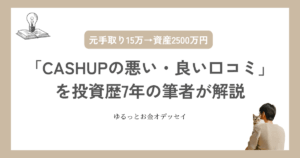「ほったらかし投資が気になるけど、どの本を選べばいいかわからない」と悩む方が増えています。
投資情報が溢れる現代、正しい知識を効率的に得るのは容易ではありません。
特に初心者の場合、専門用語の壁や情報の取捨選択に戸惑い、結局行動に移せないケースが少なくないのが現状です。
そこで本記事では、特に「長期・分散・低コスト」を重視するほったらかし投資に特化した書籍を厳選しました。
新NISA制度に対応した最新情報から、20年の実績に基づく投資哲学まで、多角的な視点で5冊を紹介します。
投資初心者が最初に抱く「本当にこれで大丈夫?」という不安を解消する、確かな指針が見つかるでしょう。
筆者のおすすめ本は、『全面改訂 第3版 ほったらかし投資術』です。難しいことは抜きにして、「とりあえず、これ!」というのがわかるでしょう。
初心者必見|ほったらかし投資におすすめ本5選
ほったらかし投資は、シンプルかつ効率的に資産を増やす方法として注目されています。初心者が投資を始める際には、適切な知識を得ることが重要です。
 ひろ
ひろそこで、筆者の独断と偏見でおすすめの本を5冊紹介します。
- 全面改訂 第3版 ほったらかし投資術
- お金は寝かせて増やしなさい
- 世界一やさしい 投資信託・ETFの教科書 1年生
- 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
- わが投資術 市場は誰に微笑むか
①全面改訂 第3版 ほったらかし投資術
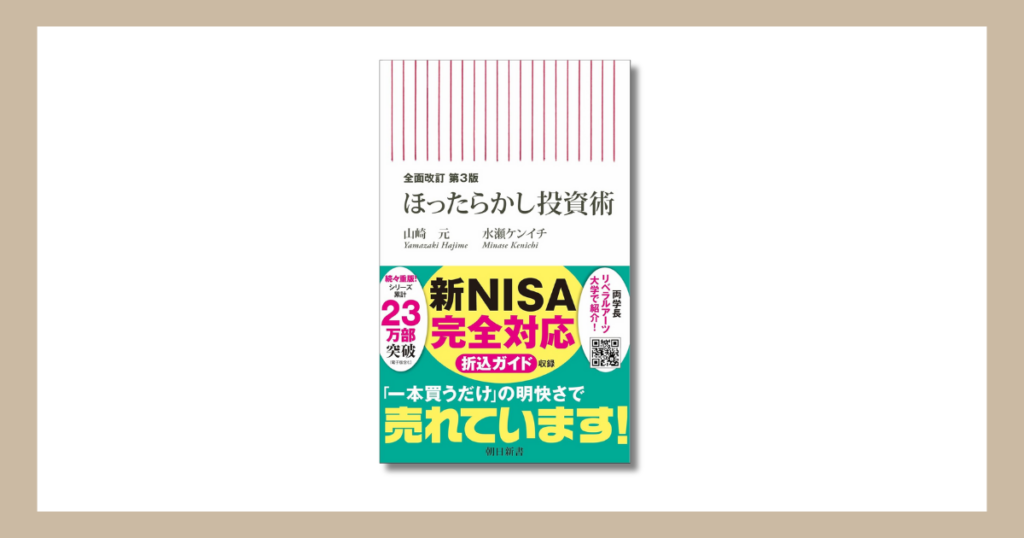
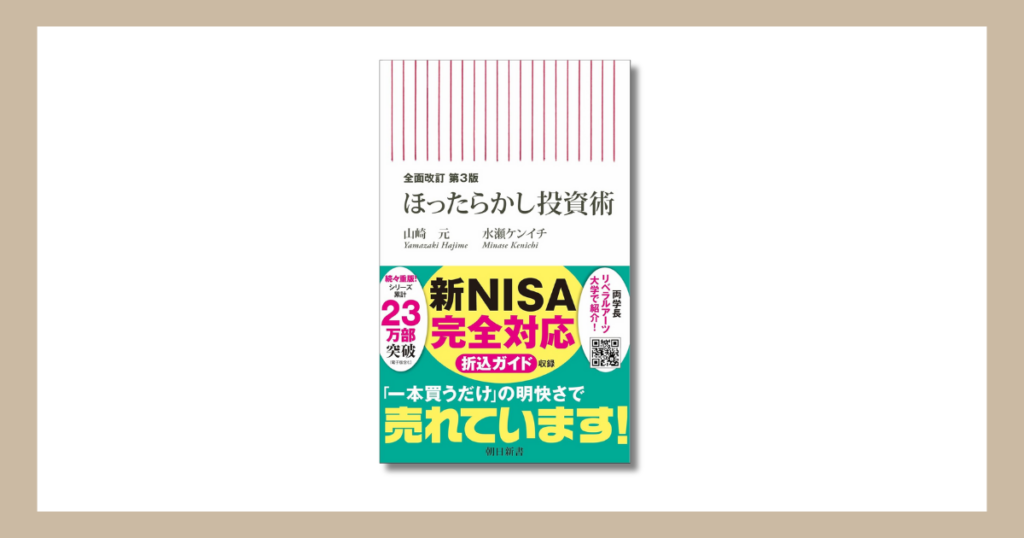
『全面改訂 第3版 ほったらかし投資術』は、山崎元氏と水瀬ケンイチ氏による初心者向けの投資ガイドです。
本書は、全世界株式インデックスファンドを活用したシンプルな運用方法を提案しており、「迷わず始められる」投資法が特徴です。
過去のデータを用いたシミュレーションが豊富で、「なぜインデックス投資が有利なのか」を説得力をもって説明しています。
具体的には、インデックス投資の基本から実践マニュアル、口座開設の手順まで丁寧に解説されているため、初めて投資をする人でも安心して学べるでしょう。
また、本書では「長期・分散・低コスト」をキーワードに、リスク管理や継続の重要性についても詳しく触れています。
さらに、著者たちの経験に基づいたアドバイスが随所に盛り込まれており、理論と実践のバランスが取れた内容となっています。
この一冊で、ほったらかし投資の全体像をつかむことができるでしょう。



筆者としては、「個別株を選ぶ必要がない」という考え方によって、投資のハードル下げてくれていると感じました。
②お金は寝かせて増やしなさい
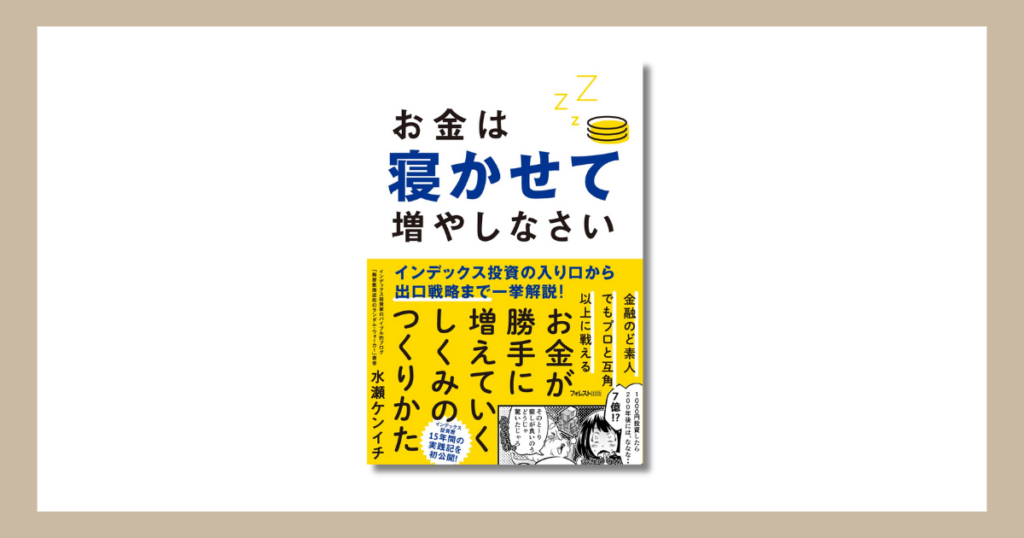
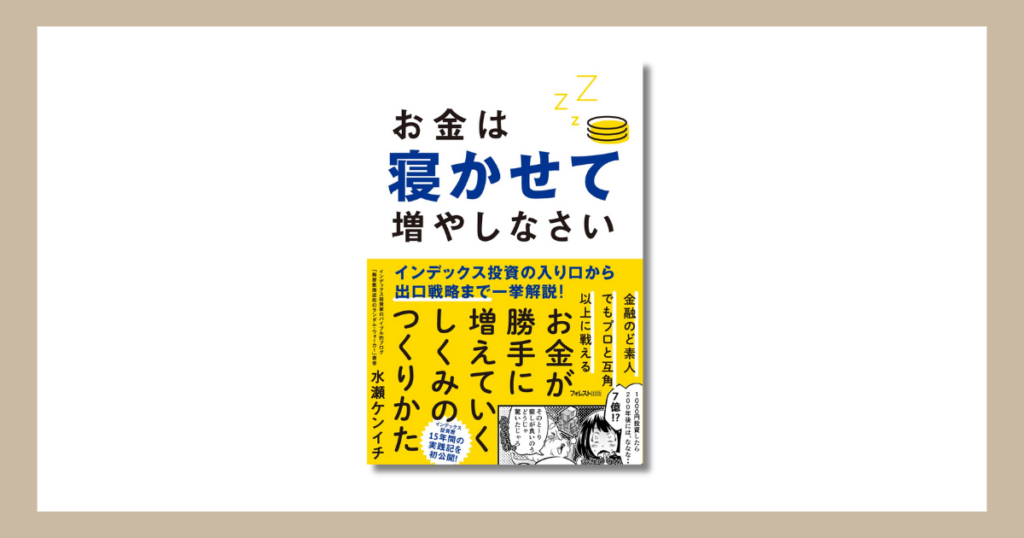
『お金は寝かせて増やしなさい』も、水瀬ケンイチ氏によるインデックス投資の実践書です。
著者自身が20年以上にわたり実践してきた経験をもとに書かれており、新NISAにも対応した改訂版では最新情報も反映されています。
本書では、インデックスファンドへの長期積立というシンプルな方法で資産形成を目指すアプローチが紹介されています。
特に「生活防衛資金」の確保や「リスク許容度」の設定など、初心者が陥りやすい問題への具体的な解決策が示されている点が魅力です。



また、第6章では「インデックス投資の終わらせ方」という珍しいテーマも扱われており、出口戦略についても学べるのがいいと思います。
投資は、出口戦略、どう終わらせるかを考えるのが難しかったりするので、その考え方を知れるのは嬉しいです。
本書は単なる理論書ではなく、著者自身の成功と失敗から得た実践的な知識が詰まっています。
そのため、「初めての一冊」としても、「運用中の確認用」としても役立つ内容となっています。
③世界一やさしい 投資信託・ETFの教科書 1年生
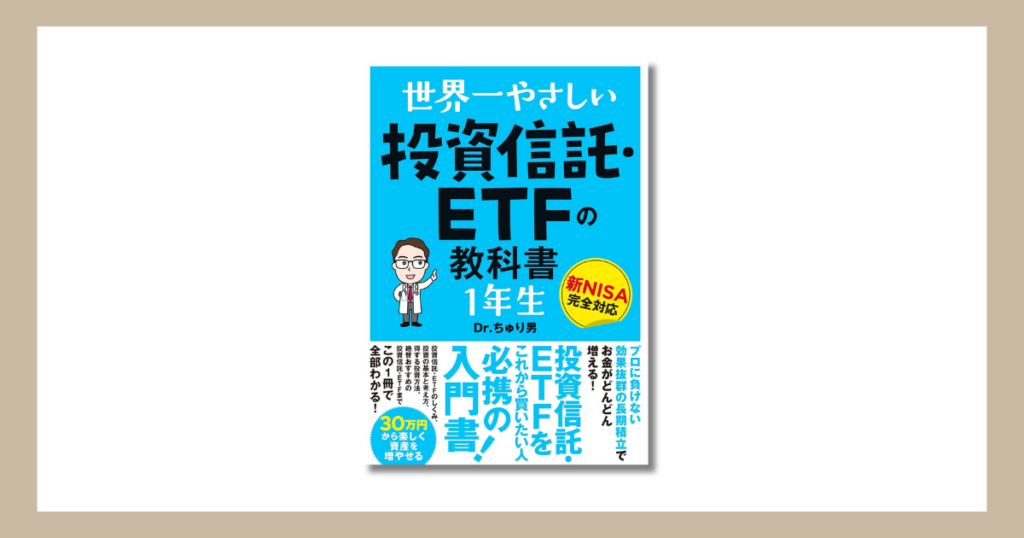
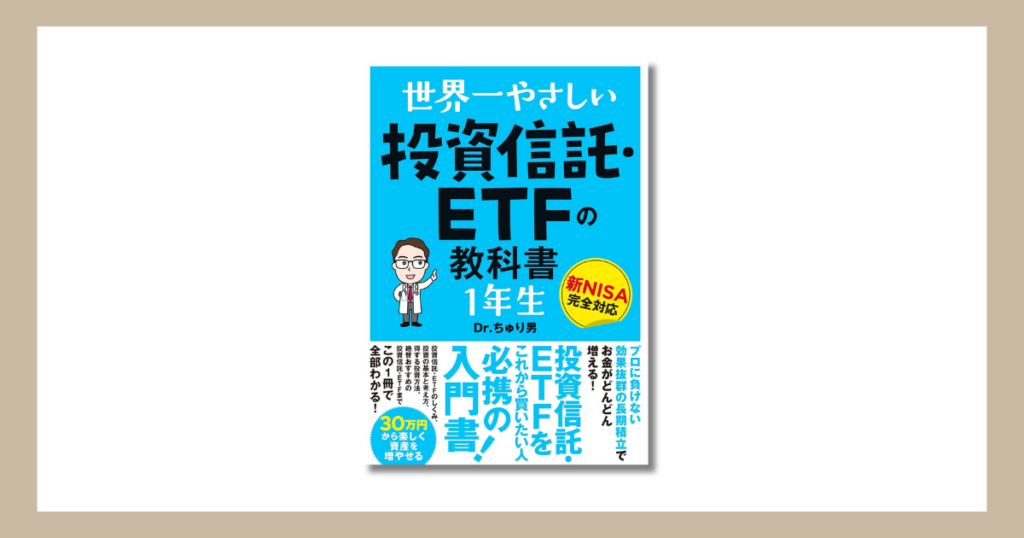
『世界一やさしい 投資信託・ETFの教科書 1年生』は、Dr.ちゅり男氏による初心者向けの入門書です。
本書は、新NISA制度の活用法やインデックスファンド・ETFの基礎知識を丁寧に解説しています。



特に図解や具体例が豊富で、「難しい専門用語が苦手…」という方でもスムーズに読み進められるのがいいと思いました。
また、おすすめの商品として全世界株式(オールカントリー)やS&P500など定番ファンドだけでなく、高配当株やテーマ型ETFなど多様な選択肢も紹介されています。
さらに、本書では「預貯金とインデックスファンドを50:50で持つ」といった初心者向けのリスク管理方法も提案されており、安全性と成長性を両立したアプローチが学べます。
ある程度投資知識がある人には物足りない可能性が高いですが、投資信託やETFを始めたい方には最適な一冊になるでしょう。
➤ 世界一やさしい 投資信託・ETFの教科書 1年生はこちら
④難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
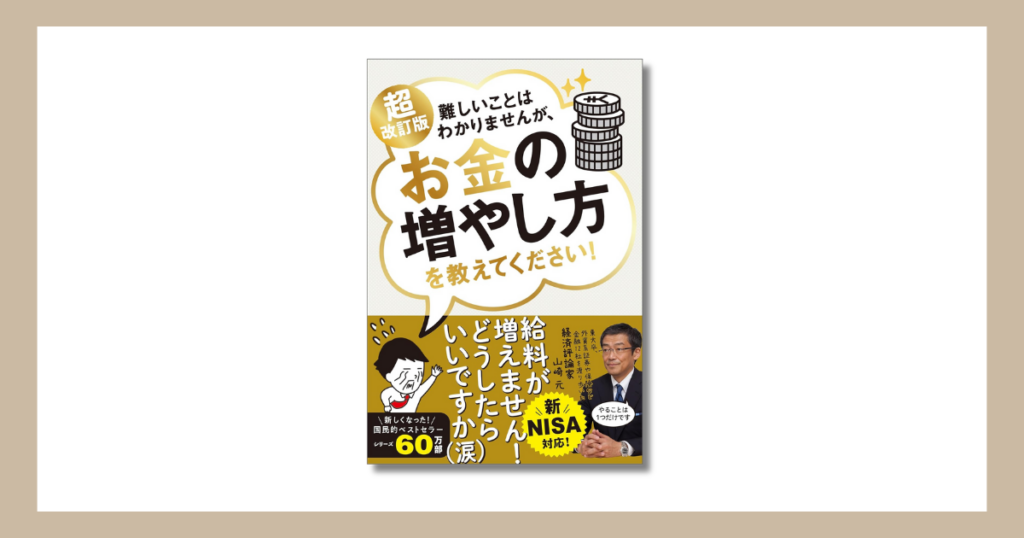
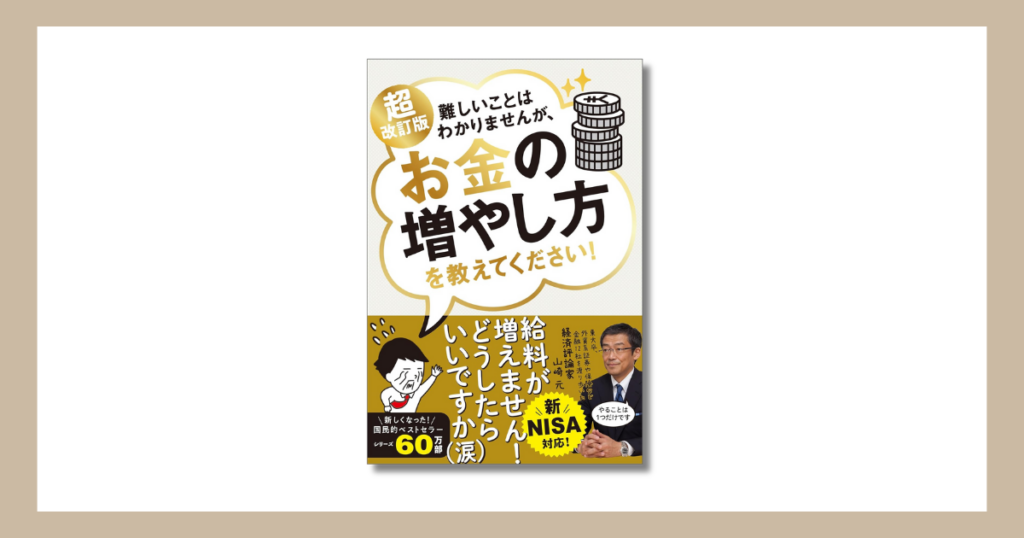
『難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』は、山崎元氏と大橋弘祐氏による会話形式の投資入門書です。
2024年新NISA制度に対応した改訂版では、全世界株式インデックスファンド「eMAXIS Slim」を使った具体的な運用方法が解説されています。
本書の特徴は「行動に直結する実践指南」にあります。
定期預金との比較から始まり、NISA・iDeCoの活用法、保険の真実まで段階的に学べる構成です。



特に「生活費の3ヶ月分を確保後、余剰資金で積立投資」という具体的なアドバイスは、初心者が最初に知るべき基本原則ですね。
投資に必要な7つのステップ(いつ・どこで・何を・どのように・いくら・どうする)がシンプルにまとめられており、行動心理学を応用した「迷わず始められる」仕組みが特徴です。
著者自身の運用実績公開やがん保険の必要性に関する異論など、従来の常識を覆す内容も含まれています。
➤ 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!はこちら
⑤わが投資術 市場は誰に微笑むか
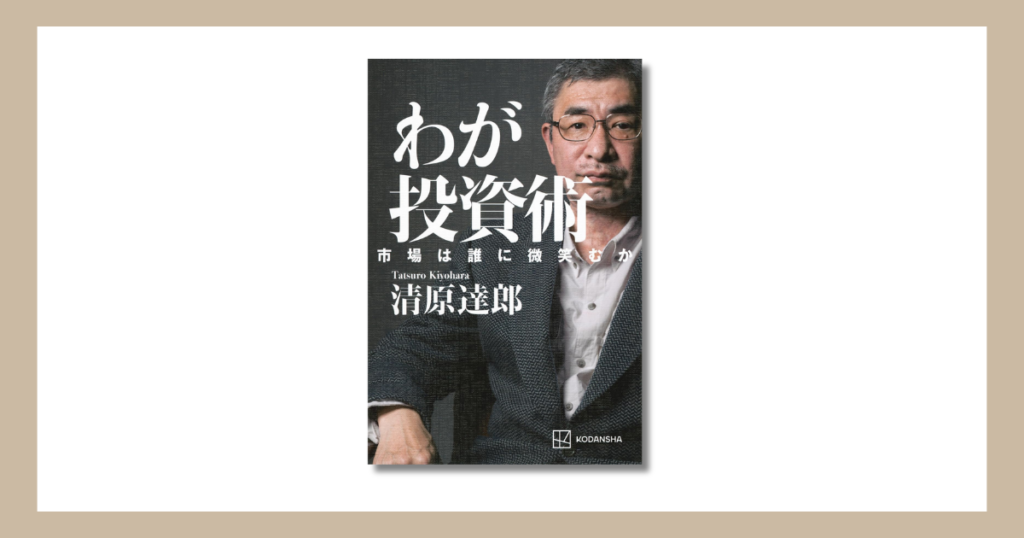
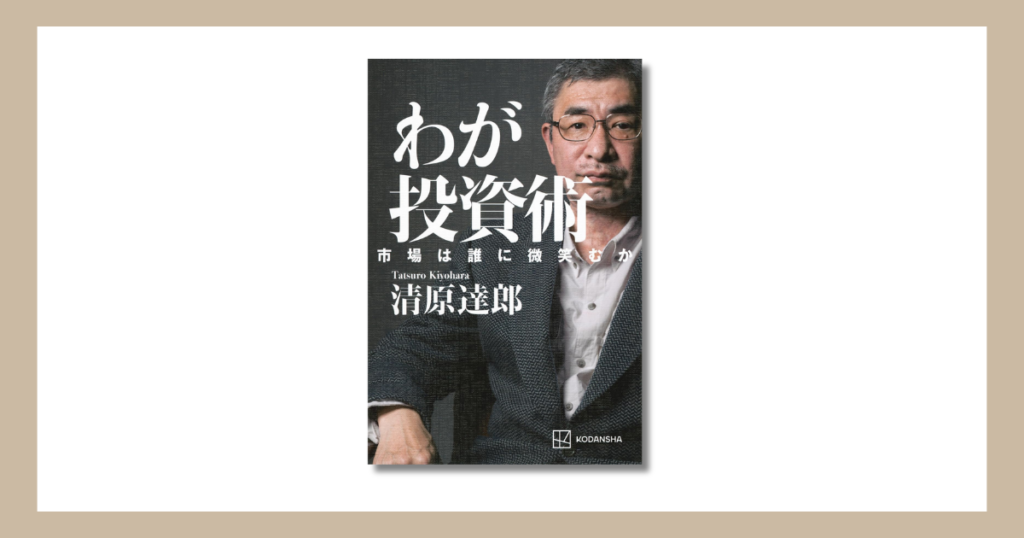
『わが投資術 市場は誰に微笑むか』は、伝説的投資家・清原達郎氏が800億円超の資産形成で得た哲学を体系化した一冊です。
新NISA完全対応で、長期投資における「失敗からの学び」を重視した内容が特徴。
本書の核心は「市場の本質的理解」にあります。
- パッシブ運用とアクティブ運用の比較
- 割安小型成長株の選定基準
- REIT運用の失敗事例
など、専門家でも把握が難しい高度なテーマを平易に解説しています。



特に「情報収集に金をかけない」「ESG投資の限界」といった逆説的アドバイスは、経験者にも新たな気付きを与えると思います。
実践編では、100万円からの運用戦略やショート売りのリスク管理など、具体的な手法が詳細に記述されています。
2024年以降の日本株市場分析や「やってはいけない投資」の章は、時代に左右されない普遍的な投資原則を学ぶのに最適です。
ほったらかし投資の本を読む際のコツ
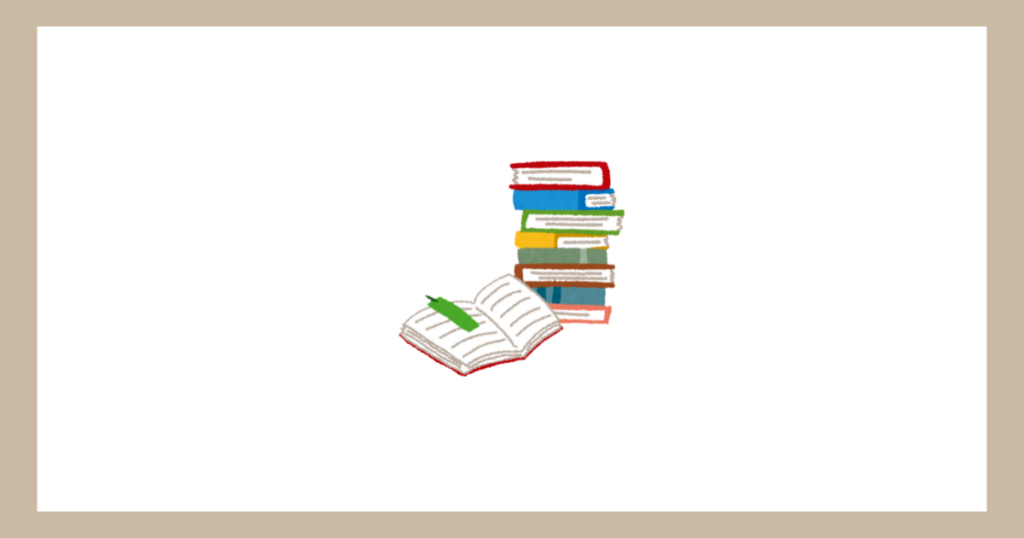
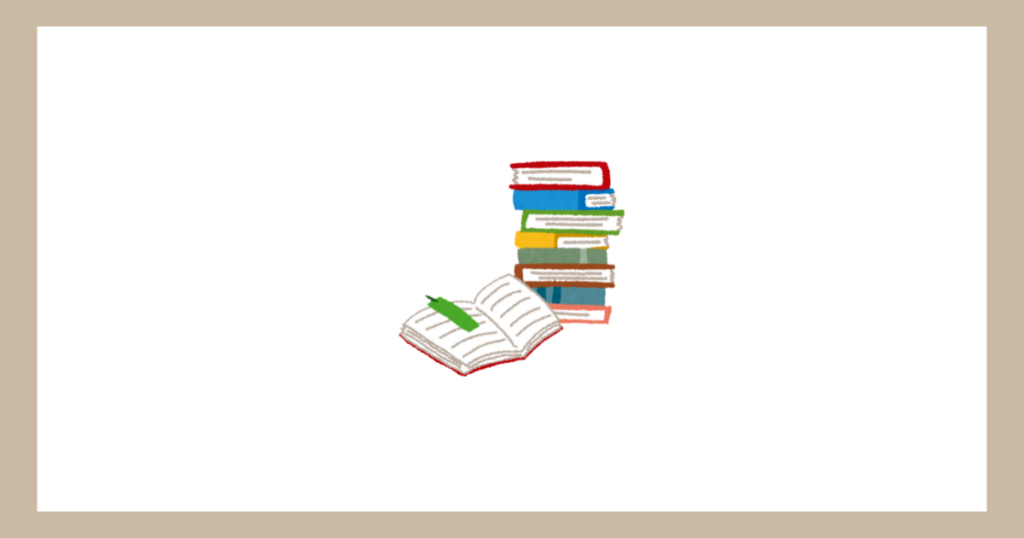
ほったらかし投資の本質を理解するには、効率的な読書法が重要です。
知識の定着を促し、実践に活かすための具体的な3つの方法をご紹介します。
- 理解できない章や内容は一旦飛ばしてOK
- 読んで終わりにせず実践に移す
- 重要な箇所はノートにメモを残す
本を読む前・最中・後に意識すべきポイントを押さえましょう。
理解できない章や内容は一旦飛ばしてOK
投資本に登場する専門用語や数式は、初心者にとって大きな障壁となります。
例えば「シャープレシオ」や「標準偏差」といった概念は、最初の段階で完全に理解する必要はありません。



簡単にメモをして、読み飛ばしても大丈夫ですよ。
重要なのは全体の流れを把握することです。
例えば、第1章の基礎理論が難解な場合、第4章の実践編から読み始めてもいいと思います。
筆者も、本を読む際は、頭から尻まで順に読むのではなく「読みたい箇所」から読んでいました。
初めから難しい話だと面白くなく、モチベーションも下がるので、読めるところから読んでいくのがいいでしょう。
また、自身のお金や投資の知識が深まっていくと、2回目に「1回目で読めなかったところが読めた」ということもあります。
大切なのは「投資の全体像」を掴むことであり、詳細な理論は実践しながらの方が良かったりしますね。
読んで終わりにせず実践に移す
投資知識は「使うことで血肉になる」と思います。
海の泳ぎ方を陸で教わったところで泳げるようにはなりません。同じように、投資も本を読んだだけでは身につかないのです。
例えば『全面改訂 第3版 ほったらかし投資術』を読んだら、直後に証券会社の口座開設を済ませましょう。
書籍で学んだ「全世界株式インデックスファンド」を1,000円から購入するだけでも、実践的な学びが得られます。
何かを学んだ後はすぐにアウトプットするのが大切です。
また、実践時には、書籍の該当ページを開きながら操作とより深く身につきます。
失敗を恐れず、少額から始めることが継続のコツと言えるでしょう。
重要な箇所はノートにメモを残す
効果的なノート作成のポイントは「3層構造」にあります。
- 第一:気付きを書き留める
- 第二:自分の言葉で要約する
- 第三:行動計画を記入する
例えば、『世界一やさしい 投資信託・ETFの教科書』を読む際、重要部分に付箋を貼りながら、後でノートに転記する方法がおすすめです。
デジタルツールを活用する場合は、EvernoteやNotionで「資産配分」「リスク管理」「おすすめ商品」などのタグ分類が有効です。
定期的にノートを見返す習慣をつけることで、知識が体系化されていきます。



筆者個人的には、紙にメモをした方が記憶に残りやすいです。
まとめ
ほったらかし投資の成功は、適切な知識の選択から始まります。今回紹介した5冊は、それぞれ異なるアプローチで投資の本質を伝えています。
『全面改訂 第3版 ほったらかし投資術』では実践的なマニュアルを、『お金は寝かせて増やしなさい』では長期運用のコツを学べるのが特徴です。
初心者向けの『世界一やさしい 投資信託・ETFの教科書』と『難しいことはわかりませんが~』は、専門用語を噛み砕いた解説が評判です。
経験者向けの『わが投資術 市場は誰に微笑むか』では、800億円を運用した投資家の哲学が学べます。
どの書籍も共通して「長期視点」「分散投資」「継続の重要性」を強調している点が特筆すべき点と言えるでしょう。
最も重要なのは、読了後の行動です。
書籍で得た知識を元に、少額からでも実際に口座を開設し運用を始めてみてください。
定期的に本を読み返すことで、市場の変動に惑わされない確かな投資家として成長できるはずです。
筆者のおすすめは、水瀬ケンイチさんの『全面改訂 第3版 ほったらかし投資術』です。
投資はなんだかハードルが高そうなものに思えますが、実際はそうでないことを教えてくれます。最初に学ぶのであればできるだけカンタンなものが絶対にいいです。